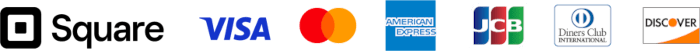不貞の慰謝料請求の不真正連帯債務って、債権法改正で「割合的清算」ってできますか?
不貞の慰謝料請求の不真正連帯債務って、債権法改正で「割合的清算」ってできますか?
不貞の慰謝料請求を受けた場合、他方配偶者と同衾者は、「不真正連帯債務」の関係にあります。ところが、令和2年4月1日に債権法が改正されました。特に、連帯債務に関わる部分には多くの改正点がありましたが、不貞の慰謝料請求の「共同不法行為」つまり、一緒に悪いことをした場合の求償関係は、従来の判例法理が妥当するのか、債権法改正に影響を受けるのか、債権法改正の経緯を学問的に専門とする弁護士が解説します。
(弁護士と息子との対話)
シュシュ:改正民法442条1項は、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する」とあるよね。
弁護士:うん。一般的には、連帯債務者さん同士だから、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず求償権を取得するということだよね。
シュシュ:そうすると、従来の判例を余り大きく変えるものではないよね。だって、もともと、連帯債務者間で求償が問題となる場面での負担部分とは「割合」を意味するのであって、「額」を意味するのではないというのが大審院の判例(大審院大正6年5月3日)だったじゃん。
弁護士:シュシュの言う通りだね。
シュシュ:問題は、「連帯債務」の民法442条1項の規定が「不真正連帯債務」にも適用されるかだね。もし適用されるとすれば、従来の判例変更となり、自己の負担部分を超えていなくても割合的に都度求償することができるようになるよね。でも、学説は分かれているみたいだね。
弁護士:共同不法行為については、債権法で意識された分野ではないから学説も対立しているよ。しかも、不真正連帯債務という概念自体が、最高裁の判例で発展したものだからね。
シュシュ:潮見先生は、「本条の規律は、改正前民法下で論じられていた不真正連帯債務にも適用される。したがって、求償権に関して、不真正連帯債務においては連帯債務であることを理由とする求償権が認められないとしてきた従来の実務を変更することとなる」として、「割合型の求償が認められる」と判例変更が行われる立場にたいだね(潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』118頁(金融財政事情研究会、2017年))。この見解によると、不貞慰謝料を同衾者が支払った場合でも、他方配偶者に都度都度割合型の求償が認められるということで求償しやすくなるね。
交通事故についても、求償権の消滅時効は、不当利得であるから、一般債権によるものとして、「不真正連帯債務者間の求償権の法的性質を一般の債権と解すると、改正民法施行後における求償権の消滅時効の起算点やその期間についても、不法行為による損害賠償債務についての民法724条は適用されず、一般の債権についての新民法166条が適用される」という見解は主流なんだ。
弁護士:ところが「求償権」は別という反対意見があるんだね。不真正連帯債務間の求償については、民法442条の類推適用によるのではないという見解なんだ。これは、上記の潮見説を真向から否定するものだね。そして、民法444条・465条1項の趣旨の類推、信義則による求償を認め、自己の負担部分を超えた支払に限定し、その超えた部分に限り可能であるとする見解があります(平野裕之『債権総論[第2版]』283頁(日本評論社、2023年))。平野説によると、従来の判例が維持されるべきという見解になり、判例法理は不真正連帯債務の求償を認めるものの(最判昭和41年11月18日民集20巻9号1886頁・最判平成10年9月10日民集52巻6号1494頁)、その範囲は、「自己の負担部分を超えて損害を賠償したとき、その超える金額」に求償を制限しているんだ(最判平成3年10月25日民集45巻7号1173頁)。
1.民法442条1項と求償を制限する平成3年最高裁判決
改正債権法442条では、不真正連帯債務における絶対的効力事由を極めて限定しています。つまり、債権は外的には個別的作用という意味合いが強まりました。
例えば、夫が妻の不貞相手の同衾者に慰藉料を請求して、同衾者は、自分は「副次的責任しかない」と昭和60年の東京高裁判決を引用して主張するケースが多かったが、債権は外的には個別的作用しかないという意味合いが強まったんだ。
これにより,債権法改正後の真正連帯債務と,改正前民法下において絶対的効力事由を限定して解釈されてきた不真正連帯債務とは,個別事由の内部的効力という観点では類似することになった。
もっとも,求償要件について,債権法改正後の民法は,真正連帯債務者間で求償権が発生するためには「自己の負担部分を超える支出」を必要としないものとしていることが確認されています(民法442条1項)。
もっとも、これが、不貞の慰謝料の求償権のように、不貞した配偶者と同衾者との間の求償権についても、ストレートに民法442条1項が適用されるかが問題とされています。
この点、民法442条1項が、不真正連帯債務における求償権の発生のためには自己の負担部分を超えて支出することを必要とした判例法理(最判昭和63年7月1日民集42巻6号451頁)を変更する趣旨のものかどうか分からないのです。
改正後は,学説の中では、「不真正連帯債務概念」を「無用」とする見解もあり、この見解によると、「求償要件」については民法442条1項に従うものとされています。
ただし、不真正連帯債務は契約で発生するものではありませんから、その概念自体は残らざるを得ないというのが私見の考え方です。
そして、不真正連帯債務における求償権の発生のためには自己の負担部分を超えて支出することを必要とした判例法理は、現在も実務上は残されています。
民事裁判でのポイント
不真正連帯債務者間の求償に関する規律を定めた債権法改正後の民法の諸規定は,基本的には,不真正連帯債務者間の求償にも適用されると理解されていました。
しかし、「求償要件」に限っては、判例法理(最判昭和63年7月1日民集42巻6号451頁参照)が発展を遂げているため、維持されるのか,これが変更されると民法442条1項に従うのか、解釈に委ねられています。
例えば,夫から,その配偶者である妻の不貞相手恋人に対する慰謝料請求において300万円の支払を命じる判決が確定し,これに応じて恋人が100万円だけ一部弁済した場合,便宜的に負担割合を各2分の1とすると,判例法理が維持されるとすれば,弁済額が150万円を超えるまでは求償できないことになります。これが、従来の実務です。
しかしながら、民法442条1項に従いますと、恋人は,妻に対し,負担割合により50万円を求償できることとなるのです。
債権法改正前の民法下の家裁実務等では,不真正連帯債務の求償請求は必ずしも多くはなかったですし、上記のような場合、分割払いの場合、求償権が現実化されることがほぼなかったのですが、今後,学説の動向を巡って求償要件が緩和されますと、求償権も意識した和解契約が求められる可能性も出てくる可能性はあるでしょう。
伝統的な実務
もともと、「不真正連帯債務」では、債務者間の「外部的」な「負担部分」ということはありませんので、原則として求償関係は生じないと考えられていました。
したがって、昔は、夫が恋人に不貞の慰謝料請求をした場合、恋人は妻に求償するということはできなかったのです。
しかし、戦後、不真正連帯債務においても求償を認める考え方が通説化して、判例も、求償を交通事故で認めるに至りましたが、その論理は明らかにされませんでした(最判昭和41年11月18日民集20巻9号1886頁)。
その後、求償の要件は、繰り返すとおり、複数の最高裁判決により、「自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき」求償できるとされています(最判平成3年10月25日民集45巻7号1173頁)。
このため、理論的には被害者の救済が最優先され、被害者は、不貞でいえば、妻からも、恋人からも回収することによって、被害回復が図ることができたのです。このように、負担割合を超えて支払をした場合に限り、かつ、その超えた部分のみしか求償ができるに過ぎないとされたのは、加害者の総資産の減少と同時に被害者保護の理念があったと思います。
令和2年からの債権法改正では、本来は、不真正連帯債務という概念を否定する目的でした。したがって、民法442条1項は、従前不真正連帯債務と考えている類型にも理論上は適用され得ることには注意しましょう。
ただし、負担割合型で求償ができるものの、不真正連帯債務の場合は、改正後は、不真正連帯債務であることを主張することにより、相不法行為者は求償に応じることを拒むことは可能であり、従来の判例が維持されるものと考えられています。
したがって、例えば、妻の立場から、恋人から求償されて、債権法改正による民法442条1項を持ち出し、割合型清算ができるといわれても、改正後も、不真正連帯債務は解釈上認められ、従前の判例を維持できるとの見解が私見の調べた限り、最も有力な見解のように思われます。薬剤師免許を取り消される行政処分です。免許が失われるので薬剤師としての仕事は一切できなくなります。
2.結論:不真正連帯債務の解釈は変わっていないとの解釈が現時点では妥当。
例えば、不貞行為をした場合、夫に対する慰謝料を賠償した恋人から妻に求償された事例において、割合的求償が認められるかというと否定することが相当です。
特に、仮に、慰謝料が300万円の場合において、300万円全額を恋人が支払い、内部的負担割合に応じて求償を求めるケースと、100万円の一部弁済しかしていないのに、妻に50万円を求償権請求するのは、比較衡量上、異なると思います。
後者のケースでは、夫は200万円がまだ未回収なのですから、共同不法行為者の一人が過失割合によって定められる負担部分に満たない負担をした場合にも、他の共同不法行為者に対して求償できることになってしまい、パブリックコメントで最高裁が指摘したように、債務者の一人から負担部分に満たない一部弁済がされた場合に、被害者の損害賠償請求権と、損害賠償金のうち自らの負担部分の一部を被害者に支払った共同不法行為者が他の共同不法行為者に対して行使する求償権との競合が生じることになり、被害者保護に欠ける結果が生じる懸念があります。
るが、部具体的にどういった問題行動をすると業務停止や免許取り消しなどの行政処分が行われるのか、実例をいくつかみてみましょう。
3.不真正連帯債務に割合的求償は認められない
改正法の下でも不真正連帯債務概念は否定されません。不真正連帯債務では、負担部分を超えた賠償をした場合にその超えた金額のみ求償できるにすぎない。民法442条1項の適用は制限解釈すべきことになります。ただし、受験生向けの本をみても、求償関係については、共同不法行為者の一人が賠償をした場合には、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、その負担部分に応じた額を他の共同不法行為者に求償できる(442条1項)というA説(潮見説)と、共同不法行為者の一人がその過失割合に従って定まる自己の負担部分を超えて賠償をした場合には、その超える部分につき、他の共同不法行為者に求償できるというB説(平野説)が並列的に紹介されています。B説の被害者保護に資する見解の方が妥当であると考えます。
4.不真正連帯債務の求償割合
不真正連帯債務の求償割合自体、戦前は観念できないものとされていました。不貞の求償の場合は5:5とされがちですが、いわゆるアディーレ理論によると、男6:女4という特に根拠のない理論もあるようです。
インターネットレベルでのものしかないですが、やはり民法719条1項前段は、「公平という観点」から「求償」を考えるものですから、過失の場合は、「過失の程度」を基準に交通事故の過失割合のような負担割合を検討せざるを得ません。
不貞のケースでいえば、不貞妻と同衾者についてはどちらもどちらという感じもしますが、個別具体的な事例においては、責任の軽重はあるでしょう。例えば、神戸市に住んでいる方が不倫のため、名古屋市の夫宅を訪れて自宅で同衾に及んだという場合は、種々の事情を考慮しても、同衾者は、名古屋市に来る義務も、配偶者の自宅で性交渉をする義務もありません。また、夫やこどものプライバシーが尊重され、家族は集団生活をする場所であることに照らすと、結果の裁量的判断といっても同衾者の方が責任は重たくなるべきでしょう。主には、主導的役割を果たしたか、中心人物であるのか、などその不法行為を引き起こすことへの原因力や因果力、寄与度も斟酌される。これらは、メタファーでは交通事故の緑本と変わらないといえます。その意味で、過失を含めて双方の違法性の度合いによるべきとする見解、違法性の程度や原動力を加えた加害行為への寄与度によって決まる見解があります。
上記事案に即すると、例えば、不貞行為をするにあたって、自宅に招き入れている場合、相対的に住居権がある妻と比較して、住居権がない同衾者の違法性の度合いが強くなるでしょう。もっとも、妻がラブホテルに行くのを嫌がり、自宅に積極的に招き入れたといった事実関係があれば、違法性について原動力を与えたのはむしろ妻の寄与度の方が大きいという判断になるのではないでしょうか。
5.結論
不貞の慰謝料請求を支払った後、「求償権」が生じることは知っているものの、債権法改正により、割合的清算が可能になった可能性があるのではないか、といった可能性をご存知の方がいることは少ないのでしょうか。この点は、現在、最高裁判例がない分野であるため、ケースバイケースで事実認定を重視したうえで、法令についても、AIでは必ずしも具体的な判断ができるとは限りません。割合的求償に応じる前に、最高裁の判例に適合的であるか、不貞問題も含めて詳しい家族法の弁護士(離婚、面会交流、相続、事業承継、憲法、こども法などを学問として専門としています)に是非、ご相談ください。