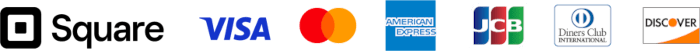夫がニューヨークで不倫関係に陥ったらどうなるのか。
結論的には、日本に帰る場合、慰謝料請求が認められてしまうとの東京高裁の判例が出ました。
公務員がニューヨークで不倫をして、不倫相手も同じく日本に帰ったというものでした。
ニューヨークでは、法令によって不貞の慰謝料が否定説が採用されているため、ニューヨーク法が準拠法の限り、慰謝料請求が認められませんでした。
前提事実として、ニューヨークで2年3か月、東京で3年6か月の不貞期間がありました。東京高裁は日本の不貞期間が長いことに着目して妻からの慰謝料請求を認めました。
東京高等裁判所令和元年9月25日
1 事案の概要
事実関係の概要は,次のとおりである。
妻である妻と夫である太郎は平成15年に婚姻した夫婦であり,平成21年までに3人の子をもうけた。太郎は日本国内で公務員として勤務し,妻は専業主婦であった。太郎は,約3年の予定で米国NY州に海外勤務することになり,平成25年3月に家族全員でNY州に引っ越した。同年10月頃には太郎の勤務先の同僚である女性花子(日本国籍・米国永住権あり)と太郎との間の不貞関係がNY州で始まり,花子は,太郎から,太郎の家族関係などを知らされた。
同年末には太郎が花子の住居で寝泊まりするのを常とするようになり,妻は太郎から花子が太郎の子を懐妊したことを告げられた。平成26年9月には花子が太郎の子を出産した。
平成27年には妻が太郎を相手方としてNY州の裁判所に短期保護命令や養育費支払調停の申立をするに至った。太郎の米国勤務が平成27年12月に終了することが決まると,YらはYらの子と3人で日本で同居することを選択して日本国内での住居を確保した。太郎は,妻と子3名の日本国内での住居は確保せず,婚姻費用(生活費)の任意の送金も一切しなかった。妻と子3名は,太郎から悪意の遺棄を受けたような状態になり,帰国後は日本国内の妻の実家に身を寄せざるを得なくなっている。不貞行為の期間は,NY州が約2年3箇月,日本が約3年6箇月である。
2 第1審判決の判断
第1審判決は,不法行為の準拠法を結果発生地法としたが,複数の結果発生地がある場合については判断を示さなかった。第1審判決は,妻と太郎との婚姻関係破綻の時期がNY州滞在中の平成27年8月であり,妻の妻としての権利侵害,婚姻共同生活平和維持の法的利益の侵害という結果発生地はNY州であるから,準拠法はNY州法であると判断した。
3 控訴審判決の判断
控訴審判決は,本件は,NY州と日本において行われた一連の一個の不法行為であり,複数の結果発生地がある場合であると判断した。その上で,複数の結果発生地がある場合における不法行為の準拠法は,最も重要な結果が発生した地の法であると判断した。結果の軽重が判断できないときは,最初の結果発生地であるとも判断したが,本件においては結果の軽重が判断できると判断しているので,傍論にすぎないことになる。
その上で,本件においては,妻と太郎一家の夫婦共同生活は基本的には日本で営まれており米国勤務は一時的なものにすぎなかったこと,不貞行為はNY州で終了せずに切れ目なく日本において継続されたこと,妻と子ら3名はNY州では不十分ながらも太郎から衣食住の提供を受けていたが,日本帰国時には悪意で遺棄されたも同然の扱いを受けたこと,花子は交際開始時に太郎の家族関係や米国赴任の事情を知らされていたこと,花子も不貞行為をNY州で終了させずに太郎及び子と同居して日本国内においても不貞行為を継続したこと,妻と太郎の婚姻関係が不貞行為開始前に破綻していたことや離婚の約束があったことを認めるに足りる証拠はなく,花子が太郎の離婚の約束の説明を真に受けたことには過失があることなどの事情があり,不貞行為期間がNY州約2年3箇月,日本約3年6箇月であることなどを考慮すると,最も重要な結果が発生した地は日本であり,準拠法は日本法であると判断した。
4 不貞行為が民事上の賠償請求の原因にならないという国内法制を採用する国や地域は多い。1個の不貞行為がそのような他国と日本とをまたいで継続的に続いた場合には,準拠法が他国法であれば賠償責任がないが,準拠法が日本法であれば賠償責任があることになるので,本件のような紛争が発生するわけである。類似の裁判例がないようであるので,参考として紹介する。
5 安藤弁護士によりますと、これをニューヨーク州を準拠法として、棄却するとなると事案が悪質なので相当ではないと思われるのです。ニューヨーク州では不貞の慰謝料請求が禁止されています。
不貞カップル間でこどもができている。
一連一体で評価されると最終行為時で判断されることになるので、従って、日本入国後に遅滞に陥るという判断になったものではないかと思われます。
6 安藤先生、日本国内に入国した後なのですが、日本入国時に婚姻関係が破綻しているとも思われます。なお、この事件は、不貞相手と不貞配偶者を共同被告として、不貞自体慰謝料を請求したものであり、いまだ離婚は成立しておりません。この点、信義則上なども考慮されているのではないか、と思われます。そのため一連一体となっています。婚姻関係の破綻が一連一体のため、判断されていない点は疑問もあります。
7 第1審原告と第1審被告Y1の家庭における夫婦共同生活は,平成15年の婚姻当初からその全期間にわたって,日本において営まれることが予定されていた。NY州における夫婦共同生活は,勤務先の都合により,平成25年3月から3年間限定の予定で行われたにすぎず,NY州勤務終了後は,日本における夫婦共同生活を続ける予定であった(渡米前の時点で帰国後に離婚する合意があった旨の第1審被告Y1の主張は,これを的確に認めるに足りる証拠がない。)。また,第1審被告Y1の不貞行為は,NY州滞在期間中に終了せず,切れ目なく日本においても継続して行われた。第1審原告及びその3人の子は,NY州においては不十分ながらも第1審被告Y1から衣食住の提供を受けていたのに対し,NY州から日本に帰国する際には,日本国内における収入及び住居の確保もされないまま,第1審被告Y1による悪意の遺棄の被害者となった。NY州における結果発生期間は約2年3箇月間であってこれ以上増えることはないのに対し,日本における結果発生期間は約3年6箇月間であって今後も時の経過とともに増加していくという関係にある。
以上の点を総合すると,日本において発生した結果は,NY州において発生した結果よりも,明らかに重大である。よって,準拠法は日本法と解すべきである。
(5) 本件は,NY州及び日本において行われた1個の一連の不法行為であり,その準拠法は日本法と解するのが相当である。
なお,仮に,日本における不法行為(平成28年1月以降)とNY州における不法行為(平成25年10月から平成27年12月まで)を分割して2個の不法行為と解すべき場合には,日本における不法行為の準拠法は日本法であり,NY州における不法行為の準拠法はNY州法であると解すべきことになる。
第3 第1審被告Y2に対する請求に関する準拠法についての判断
1 法律関係の性質決定
本件の法律関係の性質は,不法行為である。
2 準拠法の決定
(1) 不法行為の準拠法が加害行為の結果発生地であること,結果(第1審原告の婚姻生活の平和の侵害)の発生地は,平成25年10月からの約2年3箇月間はNY州,平成28年1月から当審口頭弁論終結までの約3年6箇月間は日本であること,複数の結果発生地がある場合は最も重大な結果が発生した地,結果の軽重の判断ができないときは最初の結果発生地が結果発生地となるべきことは,前記第2の2の(1)から(3)までに説示したとおりである。
(2) 本件においては,最も重大な結果が発生した地として結果発生地となるのは,NY州ではなく,日本と解するのが相当である。
前記認定事実によれば,次のようにいうことができる。すなわち,第1審被告Y2が第1審被告Y1の不貞行為の相手方となる行為は,第1審被告Y1のNY州滞在中に終了せず,切れ目なく日本においても継続して行われた。第1審被告Y2は,交際開始時に,第1審被告Y1の職業上の地位(○○省に出向中の日本の国家公務員であり,赴任期間経過後は家族とともに日本に帰国することが予定されていること)及び家庭の状況(妻である第1審原告と3人の子がいること)を知っていた。第1審被告Y2は,平成25年の交際開始後まもない時期に,第1審被告Y1の子の懐妊及び出産に直面して,第1審被告Y2及びその子が日本に帰国することにより日本における第1審原告の婚姻生活の平和を侵害することを予見していたものと推認される。平成27年後半に第1審被告Y1の日本への帰国予定が現実化した際には,第1審被告Y2は,日本国内における官舎で第1審被告ら及び子の3名が共同生活をすることを計画し,帰国後に計画を実行したものと推認される。これに伴い,第1審原告及びその3人の子の家庭の平和が著しく乱されて,経済的窮境に陥る可能性について,第1審被告Y2は予見可能であったと推認される。NY州における結果発生期間は約2年3箇月間であってこれ以上増えることはないのに対し,日本における結果発生期間は約3年6箇月間であって今後も時の経過とともに増加していくという関係にある。
以上の点を総合すると,日本において発生した結果は,NY州において発生した結果よりも,明らかに重大である。よって,準拠法は日本法である。
(3) 第1審被告Y2は,米国人の子として米国の永住権を有すること,第1審被告らには米国永住構想があったことから,結果発生地はNY州であると主張する。
しかしながら,交際をNY州内で終了させることなく,NY州内から日本国内まで切れ目なく継続させていることを考慮すると,第1審被告Y2が米国の永住権を有することを重視することはできない。また,第1審被告らの間に,具体的な実現可能性を伴う米国永住構想があったことを認めるに足りる証拠はない。
なお,第1審被告Y2は,交際開始の頃に,第1審被告Y1の家族関係と平成28年3月の帰国時に離婚予定であることの説明を,第1審被告Y1から受けていたと主張する。しかしながら,第1審被告Y1の説明は,第1審被告Y1による離婚条件の提案が記載された第1審原告宛てメールと,本気で記載したのか分からない内容の第1審原告からの返信メールに基づくものにすぎない。第1審被告Y2は,夫婦の双方が署名した離婚合意書などの文書や,第1審原告に対する直接の意思確認などの確実な確認方法をとっていない。第1審被告Y1に見せてもらった第1審原告からの返信メールは,第1審被告Y1が離婚請求の手続を開始した場合には,長期間にわたる泥沼の離婚紛争が発生することを予測させる内容のものであった。これらの点を考慮すると,NY州滞在が終了すれば離婚となる(日本における法益侵害の結果は生じない。)という第1審被告Y1の説明を真に受けたことを重視することはできない。第1審被告Y1の説明を真に受けたことについて,第1審被告Y2に過失があることは,明らかである。
(4) 本件は,NY州及び日本において行われた1個の一連の不法行為であり,その準拠法は日本法と解するのが相当である。
なお,仮に,日本における不法行為(平成28年1月以降)とNY州における不法行為(平成25年10月から平成27年12月まで)を分割して2個の不法行為と解すべき場合には,日本における不法行為の準拠法は日本法であり,NY州における不法行為の準拠法はNY州法であると解すべきことになる。
第4 第1審被告Y1に対する請求についての判断
1 日本法に基づいて判断すると,第1審被告Y1の不貞行為は,第1審原告の家庭(婚姻生活)の平和を侵害するものとして,第1審原告に対する不法行為となる。
2 第1審被告Y1は,第1審被告らが性的関係を持つようになったのは平成25年12月8日以後のことであり,当時既に第1審原告と第1審被告Y1との婚姻関係は破綻していたから,日本法によっても第1審被告Y1の行為は不法行為に当たらないと主張する(最高裁第三小法廷平成8年3月26日判決参照)。
しかしながら,前記認定事実によれば,第1審原告と第1審被告Y1との婚姻関係が破綻に向けて悪化していったのは,第1審被告らの不貞関係が第1審原告に発覚したことに原因があり,発覚前に婚姻関係が破綻していたということはできない。第1審被告Y1は,渡米前に夫婦双方が離婚意思を示し,帰国後に離婚する旨の合意が成立していたとも主張するが,そのような事実関係を認めるに足りる証拠はない。
3 婚姻関係破綻後の第1審被告Y1の不法行為責任について検討する。
婚姻関係破綻後に夫婦の一方(第1審被告Y1)と性的行為をした第三者(第1審被告Y2)は,特段の事情のない限り,他方配偶者(第1審原告)に対する不法行為責任を負わないと解される(最高裁第三小法廷平成8年3月26日判決参照)。同様に,夫婦の一方(第1審被告Y1)も,婚姻関係破綻後の第三者(第1審被告Y2)との性的行為については,特段の事情のない限り,他方配偶者(第1審原告)に対する不法行為責任を負わないと解される。
前記認定事実によれば,第1審原告と第1審被告Y1の婚姻関係は,当審口頭弁論終結時においては,破綻しているものと認定せざるを得ない。その破綻の時期は,第1審被告Y1の帰国が決まり,第1審原告がNY州で保護命令の申立てや養育費支払調停の申立てを行わざるを得なくなり,第1審被告Y1が第1審原告及びその3人の子を悪意で遺棄することを決断した平成27年11月頃であると解される。そうすると,特段の事情のない限り,平成27年11月以降の不貞行為については,第1審被告Y1は第1審原告に対する不法行為責任を負わないことになる。
そこで,特段の事情の有無について検討する。破綻の原因は,専ら,不貞行為と悪意の遺棄を実行した第1審被告Y1にある。そして,不貞行為が婚姻関係の破綻の原因となっている場合であって,破綻の前後を通じて不貞関係が切れ目なく継続している本件のような場合については,婚姻関係破綻後も不法行為責任を負うべき特段の事情があるというべきである。前記最高裁判例の趣旨は,法律婚を保護すべき必要性があるとしても,婚姻関係の破綻と無関係な破綻後の第三者との性的関係についてまで賠償責任を認めるのは,法律婚の過剰な保護に当たるから,不法行為責任の成立範囲を限定するという点にある。婚姻関係の破綻に原因を与えた不貞行為が破綻の前後を通じて切れ目なく継続している場合には,破綻後の性的関係の違法性が阻却,消滅すると考えることは,社会倫理や常識に反し,法律婚の保護の趣旨にも反するからである。
以上によれば,第1審被告Y1は,不貞行為を開始した平成25年10月から当審における口頭弁論の終結(令和元年7月)までの期間について,第1審原告の家庭(婚姻生活)の平和を侵害したことについての不法行為責任を負う。
4 本件に顕れた全ての事情を総合すると,第1審被告Y1が賠償すべき慰謝料額は300万円が相当である。弁護士費用相当額の損害は,その1割に当たる30万円が相当である。
第5 第1審被告Y2に対する請求についての判断
1 日本法に基づき判断すると,第1審被告Y1の不貞行為の相手方となった第1審被告Y2の行為は,第1審原告の家庭(婚姻生活)の平和を侵害するものとして,第1審原告に対する不法行為となる。
2 第1審被告らの性的関係は婚姻関係破綻後の平成25年12月8日以後のことであるから不法行為に当たらないとの主張が採用できないことは,第4の2において説示したとおりである。
また,前記認定事実によれば,第1審被告Y2は不貞行為開始時に第1審被告Y1の家庭の状況(妻である第1審原告と3人の子がいること)を知っていたにもかかわらず,帰国後に離婚する合意ができているという真実と異なる内容の第1審被告Y1の説明を不注意にも信じてしまったものと言わざるを得ないから,第1審原告に対する不法行為責任を免れない。
3 婚姻関係破綻後の第1審被告Y2の不法行為責任について検討する。
婚姻関係破綻後に夫婦の一方(第1審被告Y1)と性的行為をした第三者(第1審被告Y2)は,特段の事情のない限り,他方配偶者(第1審原告)に対する不法行為責任を負わないと解される(最高裁第三小法廷平成8年3月26日判決参照)。第1審原告と第1審被告Y1の婚姻関係が平成27年11月頃に破綻したことは,第4の3において説示したとおりである。そうすると,特段の事情のない限り,平成27年11月以降の不貞行為については,第1審被告Y2は第1審原告に対する不法行為責任を負わないことになる。
そこで,特段の事情の有無について検討する。婚姻破綻の原因が専ら第1審被告Y1にあることは,第4の3において説示したとおりである。そして,第三者が,自己と夫婦の一方との性的行為が婚姻関係の破綻の原因となったことを知り,又は知らないことに過失がある場合であって,破綻の前後を通じて性的関係が切れ目なく継続しているときには,婚姻関係破綻後も不法行為責任を負うべき特段の事情があるというべきである。前記最高裁判例の趣旨は,法律婚を保護すべき必要性があるとしても,婚姻関係の破綻と無関係な破綻後の夫婦の一方との性的関係についてまで賠償責任を認めるのは,法律婚の過剰な保護に当たるから,不法行為責任の成立範囲を限定するという点にある。婚姻関係の破綻に原因を与えた性的行為が破綻の前後を通じて切れ目なく継続している場合には,破綻後の性的関係の違法性が阻却,消滅すると考えることは,社会倫理や常識に反し,法律婚の保護の趣旨にも反するからである。
以上によれば,第1審被告Y2は,不貞行為を開始した平成25年10月から当審における口頭弁論の終結(令和元年7月)までの期間について,第1審原告の家庭(婚姻生活)の平和を侵害したことについての不法行為責任を負う。
4 本件に顕れた全ての事情を総合すると,第1審被告Y2が賠償すべき慰謝料額は300万円が相当である。弁護士費用相当額の損害は,その1割に当たる30万円が相当である。この総額を,第1審被告Y1と連帯支払すべきである。